マイクロプレナー®についてはこちらの記事に詳しく解説しています。

Pleasant surprises on every page! Discover new articles, displayed randomly throughout the site. Interesting content, always a click away

こんにちは!関達也です。
前回の記事では、「情報格差が経済格差よりも深刻になる時代」について書きました。
SNSのアルゴリズムが「見たいものしか見せない」構造になっていて、気づけば人は「自分に都合のいい現実」だけを信じるようになってしまう。しかも、それが社会の分断や孤立を生んでる。そんな状況を世界の事例とともに見てきました。
「情報格差が経済格差より深刻になる未来」についてはこちらの記事に書きました。

そして今、情報の取捨選択力は「ただのスキル」ではなく、「生き残るための武器」になってきています。
特に、これからの時代を「個人」で生き抜いていく人、僕らのような「ひとり起業家・マイクロプレナー®」にとっては、情報こそが最大のチャンスであり、同時に最大のリスクにもなるんです。
今回はシリーズ最終回として、「分断されたネット社会で、どうやって情報を味方につけていくか?」をテーマに、実践的なヒントをお届けしていきます!

ほとんどの人は、ネットで情報を受け取ることに慣れすぎています。
でも、ひとりでビジネスをしていくなら、「どう情報を使うか?」という視点が大切なんです。
「誰が言ってるか」「何を根拠にしてるか」「感情的になってないか」、こういう視点で情報を見るクセをつけましょう。
僕は、情報ソースを3段階で見てます。
このフィルターを通すだけで、ムダな情報に振り回されにくくなるんです。
たとえば、「ChatGPTの使い方」を調べただけで満足していませんか? それを自分のビジネスやコンテンツにどう落とし込むかまで考えることで、初めて「価値のある情報」になるんです。
僕自身も、新しいツールを見つけたら「これ、自分の事業にどう活かせる?」ってすぐ試してみます。 「学ぶ→使う→検証する」のループが、個人で生き残るコツです。

ひとり起業家・マイクロプレナー®にとって、「誰から情報を得るか?」と同じくらい、「誰にどう発信するか?」が重要なんです。
ネットの世界では、「誰が言っているか?」がすべてです。 だからこそ、自分が発信する情報の信頼性を大事にする必要があります。
一貫したテーマで、自分の言葉で、自分の体験から発信する。 これを積み重ねることで、あなた自身が「信頼される情報源」になれるんです。
全部のSNSをやろうとしても、うまくいきません。 僕はブログとYouTubeに集中しています。自分の「好き」と「得意」が合う場所で深く発信するのがコツです。
顔出しが必須か?とよく聞かれますが、答えはNOです。 でも、どんなキャラで、どんな信頼を積み上げていくかは決めておくべきです。
「信用できそう」「一貫性がある」と思ってもらえる発信設計を考えることが、ブランド作りの第一歩です。

ここが今回のいちばん重要なポイントです。
分断された社会では、「誰に刺さるか?」が超クリアになります。だからこそ、マスではなく、「共鳴する少数」を見つけたもん勝ちなんです。
例えば「40代で地方移住した人向けの副業ノウハウ」とか、「Z世代×AI活用術」みたいに、超ピンポイントなテーマの方が信頼と反応が得やすいんです。
社会がパラレル化してる今こそ、「特定の世界観に刺さる情報」を出していくことが、最強の戦略なんです。
専門的すぎる情報を、一般の人にもわかりやすく伝える人って、今すごく価値があるんです。
たとえば、「ChatGPTの英語の論文を、わかりやすく要約して日本語で発信する」とか、「法律や金融の専門家が、一般人向けにかみ砕いて発信する」とか。
この橋渡し役になるだけで、十分にビジネスは成り立ちます。
今は情報が多すぎて、「自分に必要な情報がわからない」という人が激増しています。 そういう人たちに向けて、「信頼できる情報だけをまとめて届ける」サービスを作るのもアリです。
たとえば、
こういった「情報の編集ビジネス」は、個人でも十分始められます。
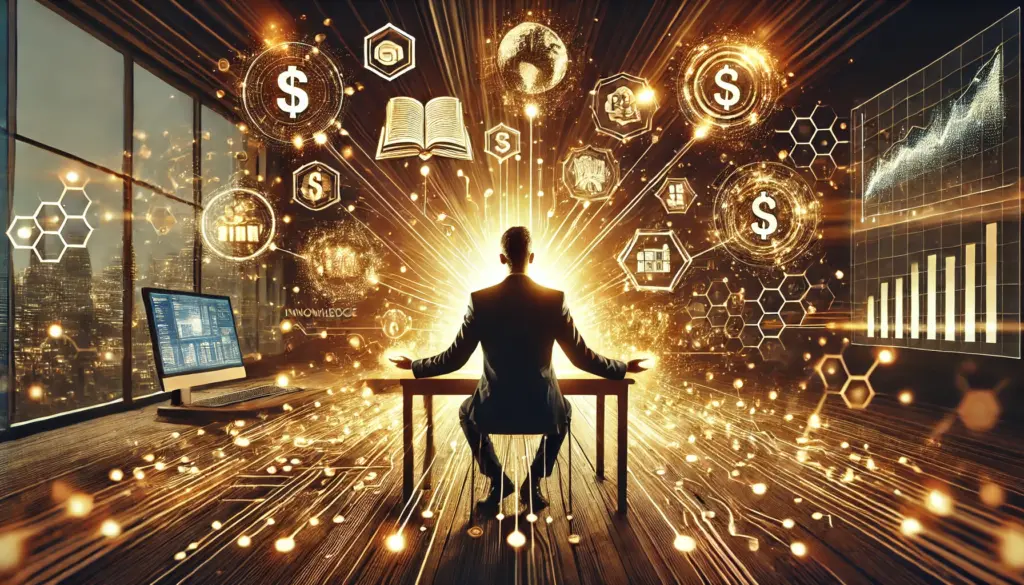
このシリーズでは、メディアの分裂、フェイクニュース、情報格差、そして分断社会の未来を見てきました。
そして最後に伝えたいのは、これだけ情報が混乱している今だからこそ、僕たちひとり起業家・マイクロプレナー®は「情報」を最大の武器にできるということです。
受け身じゃなく、選び、使い、発信する。 信頼を積み上げ、必要な人に届ける。
それができる人は、どんな時代になっても、自分の道を切り開いていけるんです。
あなたはどんな「情報の世界」で、どんな「価値ある発信」を始めますか?
僕はこれからも、「自分の頭で考える力」と「行動する力」で、地方でも、ネットの海でも、自分らしく生きていきます。あなたも、今日から一歩を踏み出してみてください。
マイクロプレナー®についてはこちらの記事に詳しく解説しています。

第一回:メディアの分裂が始まった ─「オールドメディア vs. ニューメディア」の時代へ

第二回:ホワイト社会が強まる時代に、「ルール社会 vs ストーリー社会」の分断が生まれている

第三回:ニューメディアの中の分類─「フリーメディア」と「カオスメディア」
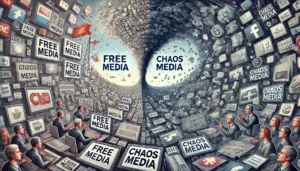
第四回:炎上した人はなぜ消えない?─テレビとネットの矛盾する倫理観

第五回:フェイクニュースはなぜ止まらない?拡散の仕組みとネット規制の未来

第六回:分断は避けられない─情報格差が経済格差より深刻になる未来

第七回:ネット時代を生き抜く─ひとり起業家・マイクロプレナー®のための情報戦略


こんにちは!関達也です。
前回の記事では、「フェイクニュースはなぜ止まらないのか?」というテーマで、ネットの構造、SNSのアルゴリズム、そして人間の心理が絡み合って、嘘の情報がどんどん広がってしまう背景を掘り下げました。
また、世界各国で進むネット規制や、フェイクが生み出す未来の3つのシナリオ─ホワイト化、カオス化、そしてパラレル化についても考察しました。
「フェイクニュースはなぜ止まらない?拡散の仕組みとネット規制の未来」についてはこちらの記事に書きました。

その中で僕が特に気になったのは、「情報の世界が分裂している」ということなんです。
同じ国に住んでいるのに、見ている現実がまったく違う。テレビを信じる人、YouTubeを信じる人、それぞれが「自分の世界」に閉じこもっている。
これはもう、“分断”と言っていい状態ですよね。
今回のテーマは、その分断がこれからどう進んでいくのか? そして、なぜ「情報格差」が「経済格差」より深刻になり得るのか? という点を掘り下げていきます。
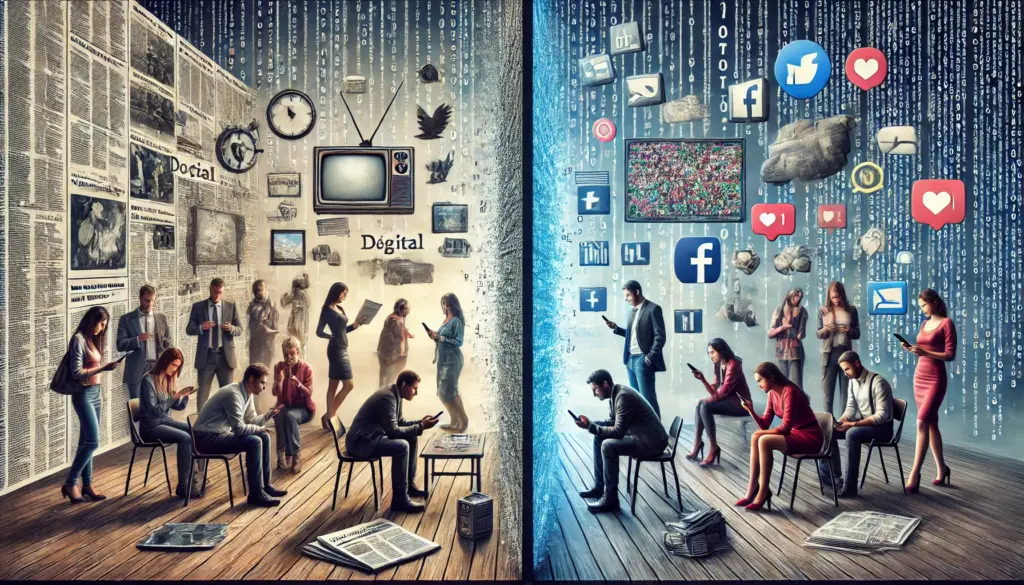
僕らの社会は今、静かに、でも確実に「情報の分断」が進んでいます。
その大きな原因は、テクノロジーの進化と、アルゴリズムの最適化なんです。
SNSやYouTubeは、「あなたが見たい情報だけ」を表示する仕組みになっています。
だから、一度“ワクチン反対”の動画を見たら、次から次へと関連動画が出てくる。Xでも、自分と同じ考えの人ばかりがタイムラインに並ぶようになります。
これ、めちゃくちゃ便利に見えるけど、実は「違う意見を見るチャンス」がどんどん減っていくんですよね。
ルール社会なら「事実」で議論できた。でも、今はストーリー社会。大事なのは「共感できるかどうか」です。
だから、「私たちが傷つけられた!」「あの人たちは悪だ!」と感じると、すぐ敵と味方に分かれてしまう。感情が引き金になって、分断が深まるんです。
面白いのは、誰かに強制されたわけじゃないんですよね。僕ら自身が、「こっちの情報の方がしっくりくる」「この人の言うことは信じられる」と思って、勝手に自分の現実を選んでいる。
つまり、分断って自然現象なんです。だからこそ、「避けられない」って話になるわけです。
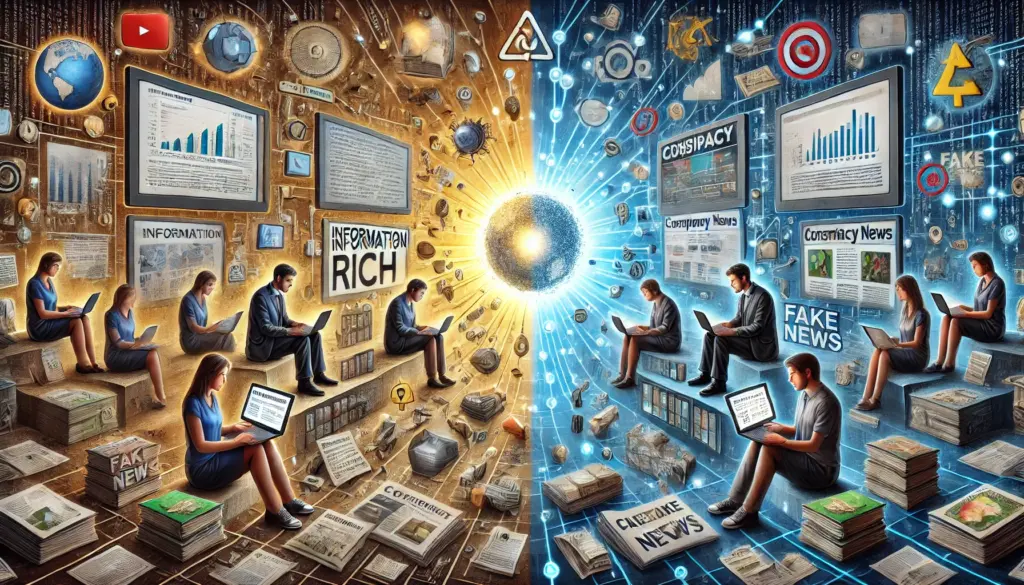
格差というと、まず「お金のあるなし」が思い浮かぶと思います。
でも、これからの時代により怖いのは、「正しい情報にアクセスできるかどうか」という差なんです。
たとえば、詐欺にあいやすい人って、「怪しい情報に弱い人」ですよね。逆に、リテラシーが高い人は、怪しい情報に飛びつかないし、騙されない。
つまり、情報格差って“判断力の差”なんです。
投資で失敗しても、また稼げばいい。でも、間違った情報を信じて行動すると、大事な人間関係を失ったり、社会から孤立したり、取り返しのつかないことになることもあるんです。
「〇〇さんが言ってたから」「SNSで流れてきたから」「なんとなく信用できそうだから」
こんなふうに、“自分の頭で考えない人”が増えてくると、社会全体が簡単に操作されてしまいます。
情報の世界では、気づかないうちに「自分で選んでるつもりで、選ばされている」ことがたくさんある。これが一番怖いところなんです。

僕は以前より地方に住んだり移動したりしながら、ネットで仕事をしてきました。だから、リアルの地域社会と、ネット上のコミュニティを両方見てるんですよね。
その中で強く感じるのが、「現実が一つじゃなくなった」ということです。
テレビ中心の人は、「マスメディアが言うこと=正しい」と思ってる。 でも、SNS中心の人は、「テレビはもう信用できない」「リアルな声はSNSにある」と考える。
これは、もう話が通じないレベルなんです。
たとえば、地方で「テレビや新聞の情報しか見ない人」と、「YouTubeやVoicyで最新の知見を吸収してる人」がいたとしたら、仕事のやり方も、行動力も、圧倒的に差がつきます。
情報の取り方ひとつで、人生の方向がガラッと変わってしまう。これが、今の時代の新しい格差なんです。
今は地方に住んでいても、どんな情報にもアクセスできるし、どんな生き方もできる。逆に、東京に住んでいても、情報に無関心だと「狭い世界」で生きることになる。
つまりここが面白くて、「どこに住むか」より「どの情報空間に住むか?」が、これからの人生を決めるんです。

情報分断は日本だけで起きているわけではありません。むしろ、海外ではその深刻さがより顕著です。
アメリカでは、共和党支持者と民主党支持者の間で、見ているニュースメディアがまったく違います。
CNNを信じる人と、FOXニュースを信じる人では、同じ事件についても“まったく別の現実”を語るようになっているんです。
たとえば、2020年の大統領選では「不正があった」と信じた人が数千万人規模で存在し、実際に2021年にはトランプ支持者による連邦議会襲撃事件が起きました。これは「フェイクが現実を動かした」典型例であり、ストーリー社会が極限まで進んだ結果とも言えます。
韓国では、若者を中心にSNSの影響力が非常に強く、検察改革や不動産政策をめぐって政府に対する不満がXやYouTubeで一気に拡散されました。
2022年の大統領選でも、ネット上のバッシングが現実の投票行動に直結する例が多く見られました。
さらに、政府への抗議デモや集会がSNSから自然発生的に広がるなど、「ネット世論が現実政治を動かす力」を持つ社会になっています。
情報の出どころが多様化したことで、韓国でも複数の現実が共存する状態になっているんです。

ここまで読んできて、「なんか怖いな…」と思った人もいるかもしれません。でも、怖がる必要はないんです。
大事なのは、「何を信じるか?」を人任せにしないこと。「どの情報が本当か?」を、自分の頭で判断すること。
僕らができるのは、情報を選ぶ力を磨くこと。そして、分断された社会の中でも、相手の立場を想像すること。
これからの時代、「経済格差」よりも「情報格差」があなたの未来を左右します。だからこそ、自分の情報の世界を、ちゃんと意識して選びましょう。
さて、次回はいよいよ最終回。情報が分断され、フェイクが飛び交うこの世界で、僕たち「ひとり起業家(マイクロプレナー®)」や「個人」はどう生きるべきか?
ネットを活用して生き抜くための戦略を、実践的な視点でお届けします。お楽しみに!
「ネット時代を生き抜く─ひとり起業家・マイクロプレナー®のための情報戦略」についてはこちらの記事に書きました。


こんにちは!関達也です。
前回の記事では、「テレビとネットの倫理観の違い」に注目し、不祥事でテレビから消えた人たちが、なぜネットでは逆に人気者として復活するのかを掘り下げました。
「炎上した人はなぜ消えない?─テレビとネットの矛盾する倫理観」についてはこちらの記事に書きました。

テレビはルール社会の象徴で、「正しさ」を最優視します。
でも、ネットはストーリー社会で、「共感」や「物語」があれば支持される。だからこそ、「炎上=終わり」じゃなくて、「炎上=始まり」になる時代になっているんですよね。
そして今回のテーマは、そのネット社会のもう一つの大きな課題である「フェイクニュースがなぜ止まらないのか?」についてです。
僕自身、ネットを使って情報発信しながらも、「これはさすがに危ないな……」と感じる場面が増えました。特にカオスメディアやSNSでは、誰でも簡単にデマを拡散できてしまう。
なぜ、こんな社会になってしまったのか? 今回はその構造と、これからどうなるのかを一緒に考えていきたいと思います。

フェイクニュースが拡散する理由には、人間の本能的な心理が関係しています。
「えっ!?」「マジかよ!」と思わせるような情報ほど、シェアされやすいんです。人は自分が驚いたことを、誰かにも伝えたくなるものなんですよね。
論理的に正しいかどうかより、「なんかその気持ちわかる!」と思える話のほうが、信じたくなる。これはストーリー社会の特徴でもあります。
人は、自分の考えや立場を肯定してくれる情報に安心する傾向があります。だから、反対の意見やデータを見ようとしない。「自分が信じたいものを信じる」時代なんです。
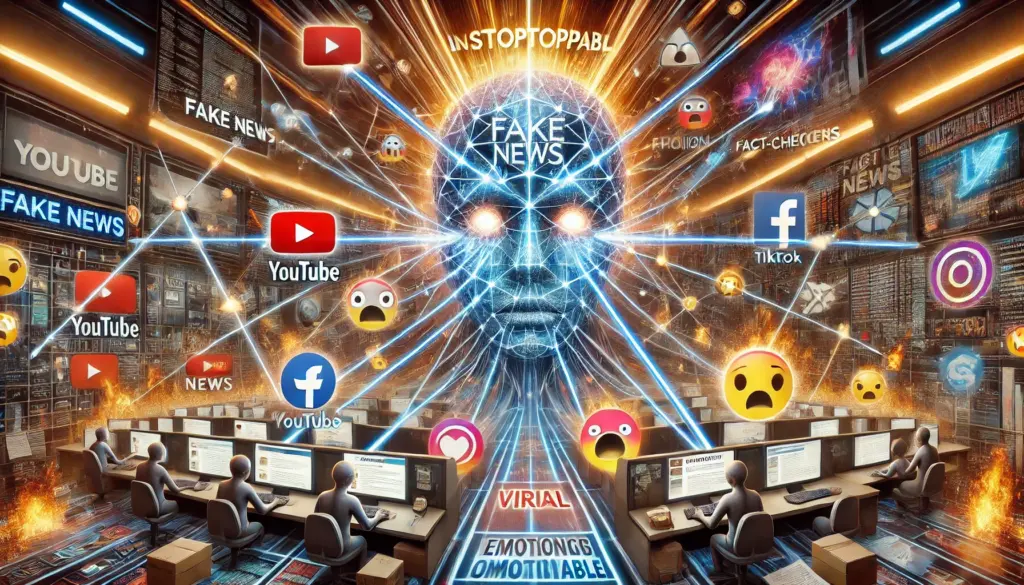
個人の心理だけでなく、ネットの仕組みそのものがフェイクの拡散を後押ししています。
YouTube、X、TikTokなどのSNSは、「いいね」や「シェア」が多い投稿を優先表示する仕組みです。だから、感情を動かす投稿、特に怒りや不安を煽るような情報が伸びやすいんです。
フェイクニュースは即拡散されるのに対して、ファクトチェックには時間がかかる。しかも、訂正が出てもほとんどの人は見ない。「ウソの方が早く広まる」というジレンマですね。
SNSや動画サイトは、ユーザーの滞在時間やエンゲージメントが収益につながる構造。だから、事実かどうかより「バズるかどうか」が最優先になってしまう。フェイクが止まらないのも当然なんです。

このまま放っておいたらどうなるのか? 僕が特に危惧しているのは、社会全体が「何を信じていいか分からなくなる」状態です。
何を見ても「それって本当?」と疑うようになる。信頼できる情報がなくなると、人は不安と混乱に陥ります。
違う世界観を信じる人たちが、それぞれのフェイク情報に引っ張られ、まったく話が通じなくなる。アメリカのQアノンや陰謀論のように、「現実が分裂する」状態が起きかねません。
医者が言っても信じない。専門家よりもインフルエンサーの方が影響力を持つ。こんな状況では、社会の制度そのものが揺らいでしまいます。
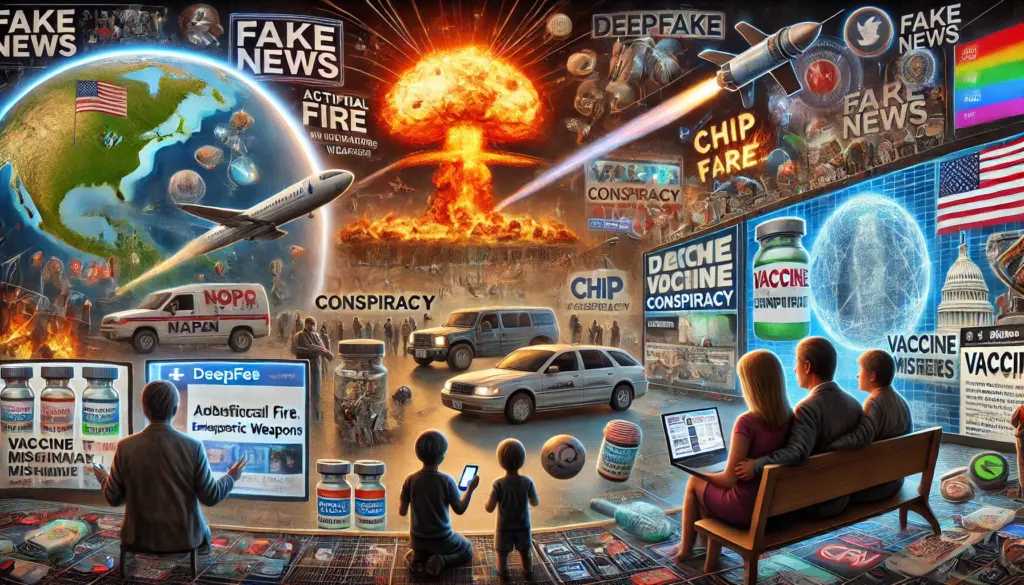
ここで、最近実際に拡散されたフェイクニュースをいくつか紹介します。
ネット空間の「信じたくなる嘘」が、どれだけリアルに社会へ影響しているかが分かります。
2024年の能登半島地震では、「火災は人工的に起こされた」「電磁波兵器が使われた」といった科学的根拠のない情報がX(旧Twitter)を中心に拡散されました。
多くの投稿がリツイートされ、SNS上で一定の共感を集めましたが、実際には事実ではないことが判明しています。
一部では「こうした情報が救援活動への不安や混乱を招いた」と指摘されています。
2024年の米大統領選では、AIによって作られた候補者の偽映像(不適切発言や行動を装ったもの)が複数出回りました。
ファクトチェックの前にSNSで拡散され、候補者の印象や支持動向に影響を与える可能性があると報道されています。
こうした「本物に見える嘘」が選挙の公正性を揺るがしかねないと、米国内外で懸念されています。
「ワクチンにはマイクロチップが埋め込まれている」「接種者は数年以内に死亡する」といった根拠のない陰謀論が、2023年末から2024年にかけてSNSで再び拡散されました。
これらは科学的に否定されており、各国の医療機関や政府も注意喚起を行っていますが、SNSでは依然として強い影響力を持ち続けています。
これらの事例を見ると、フェイクニュースは単なる“間違った情報”ではなく、人の心理に巧妙につけ込んだ“拡散されるためのストーリー”になっていると分かります。

この問題に対して、すでにいくつかの国では「規制」に動いています。
デジタルサービス法(DSA)で、プラットフォームに対してフェイクニュースの削除や説明責任を課す動きが進んでいます。
政治的発言の自由が強いため、規制はやや消極的ですが、プラットフォーム側が自主的に誤情報を警告表示するなどの対応を強化中。
国家による強力な情報統制。フェイク以前に、政権批判すら許されない環境。
明確な法規制はまだ弱い。ただし総務省やプラットフォーム各社が、自主的なガイドライン策定に動いています。

これからネット社会はどこに向かうのか?
僕は次の3つのシナリオがあると思っています。
現実的には、3番目の「パラレル化」が一番ありそうです。
事実を重視する人は「ホワイト情報ゾーン」に、刺激や共感を求める人は「カオス情報ゾーン」に住む。それぞれの現実が並行して存在するようになるかもしれません。
フェイクニュースが止まらないのは、個人の問題ではなく、社会構造とテクノロジーが生んだ必然です。
だからこそ、僕らが身につけるべきなのは「すぐ信じない」「自分で調べる」「情報の出どころを見る」といった「情報を見抜く力」なんです。
さて、次回は「分断は避けられない─情報格差が経済格差より深刻になる未来」について深掘りしていきます。
「分断は避けられない─情報格差が経済格差より深刻になる未来」についてはこちらの記事に書きました。


こんにちは!関達也です。
前回の記事では、「ニューメディアの中にも“フリーメディア”と“カオスメディア”がある」という話をしました。情報の自由さが魅力のニューメディアですが、その中でも発信の姿勢や情報の質は大きく異なるんです。
「フリーメディア」と「カオスメディア」についてはこちらの記事に書きました。
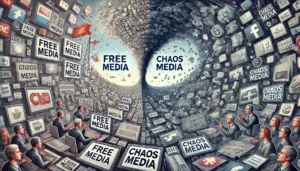
そして今回のテーマは、そのニューメディアの中で特に目立つ現象である「テレビで炎上・抹殺された人が、なぜかネットでは復活する」についてです。
たとえば、不祥事でテレビから姿を消したタレントが、YouTubeやNetflixで堂々と活動していたり、むしろ人気者になっていたりしますよね。
僕も最初は「え、なんでこの人まだ見かけるの?」って不思議だったんです。でも、これって今のメディアのあり方と、社会の倫理観の“ねじれ”が生んだ現象なんです。
今回は、その背景を「テレビとネットの倫理観の違い」から掘り下げていきます。

テレビというメディアは、まさに“ホワイト社会”の代表です。
たとえば芸能人が不倫したり、薬物に関わったりすると、番組は即降板。スポンサーが離れることを恐れて、番組側が先回りして自主的に処分する。まさに「正しくなければならない世界」ですよね。
この背景には、岡田斗司夫さんが言うように「ホワイト社会」の価値観が色濃くあるんです。
こうした価値観が、テレビの倫理を形作ってきたんです。
ホワイト社会についてはこちらの記事に書きました。


一方、ネットは真逆なんです。どれだけ炎上しても「ストーリーがあれば生き残れる」社会です。
不祥事を「物語化」することで、むしろ新しいファンを獲得する。まさに「ストーリー社会」の力なんですよ。
たとえば、テレビでは干されたタレントが、
という展開で、視聴者の共感や支持を集めるんです。
「正しいこと」よりも「納得できるストーリー」があるかどうかが、ネットでは重要になる。だから炎上しても、そこから「再生の物語」を紡げる人は、ネットで生き残れるんですよね。

このテレビとネットの倫理観の違いが、「炎上=終わり」ではなく「炎上=始まり」になる構造を作っているんです。
この「ねじれ」のせいで、視聴者の中には混乱が起きていますよね。
「え? この人って干されたんじゃなかったの?」「テレビではダメだけど、ネットではOKなの?」って。
でもこの「ねじれ」が今のメディア社会の本質なんです。

実際、炎上をバネにしてネットで再生した人って、かなり多いですよね。
テレビでは謝罪会見後、表舞台から姿を消したけど、YouTubeではコラボやグルメ企画で大成功。
地上波では姿を見かけないけど、ネットではしれっと活動再開。
活動休止後もNetflixのドラマに出演し、「テレビではNGでもネットではOK」という状態に。
これって、もう「テレビの世界に戻る必要すらない」というメッセージと思いませんか?
つまり、炎上や不祥事って、ある意味では「別の舞台へのキャリアチェンジ」のきっかけになっているんです。
ネットの特徴として、「自分の物語を語れること」があります。テレビでは編集された一部しか映らなかったけど、ネットでは1時間でも2時間でも、自分の言葉で説明できる。
しかも、視聴者は「巨大メディア vs 一人の個人」みたいな構図に共感しやすい。だから、炎上した人が「個人として再出発」すると、意外と応援されるんですよね。
これは「共感」がベースにあるストーリー社会だからこそ可能な現象です。

では、今後どうなっていくのでしょうか?
視聴率が下がり、スポンサーも「数字さえ取れればOK」となれば、テレビも多少グレーな人を使い始めるかもしれません。
逆に、YouTubeも広告主の意向で「クリーンなチャンネル優遇」が進み、暴露系や過激系は規制される可能性があります。
でも僕は、この2つが逆方向に歩み寄る未来よりも、むしろ
テレビとネットは、異なる価値観を持ったまま分裂し続ける
そんな未来の方がリアルだと思ってます。
つまり、「清潔さ」を求める人はテレビを見て、「人間臭さ」や「物語」を求める人はネットを見る。どちらかが消えることはなく、価値観に応じた棲み分けがどんどん進んでいくと考えています。
「ルール社会 vs ストーリー社会」という対立は、今回のテーマにもそのまま当てはまります。
テレビはルール社会の最前線。ネットはストーリー社会の実験場。炎上を“終わり”ではなく“始まり”に変える力があるのが、ストーリー社会なんです。
僕自身、ネットでビジネスをやってきて、何度も思ったのは、「正しさ」よりも「共感の力」が時代を動かしているということです。
これからの時代、自分のストーリーを語れる人こそが生き残る、そう感じています。
さて、次回は「フェイクニュースが止まらない理由」と「今後のネット規制」について考えていきます。なぜ嘘の情報がここまで広がるのか? 本質に迫っていきます。お楽しみに!
「フェイクニュースが止まらない理由」と「今後のネット規制」についてはこちらの記事に書きました。


こんにちは!関達也です。
前回の記事では、「ルール社会 vs. ストーリー社会」の対立について書きました。
「ルール社会 vs ストーリー社会」の対立についてはこちらの記事に書きました。

かつては、テレビや新聞といったオールドメディアが情報の中心でしたが、YouTubeやX(旧Twitter)、TikTokなどのニューメディアが台頭し、「何を信じるか?」が人によって大きく変わってきました。
ルール社会は「事実や論理に基づいた情報」を重視する一方、ストーリー社会は「共感や感情に訴える物語」を重視します。
この対立が、情報のあり方を大きく変えています。
そして、この流れの中で、ニューメディア自体も「すべてが同じ性質を持っているわけではない」ことが見えてきます。
ニューメディアの中には、独立系ジャーナリズムや専門家による解説を発信する「フリーメディア」がある一方で、炎上や陰謀論、デマが拡散しやすい「カオスメディア」も存在します。
今回の記事では、この2つのメディアの違いを整理し、なぜカオスメディアが拡散されやすいのか、そして私たちはどのように情報を選び取るべきなのかを考えていきます。
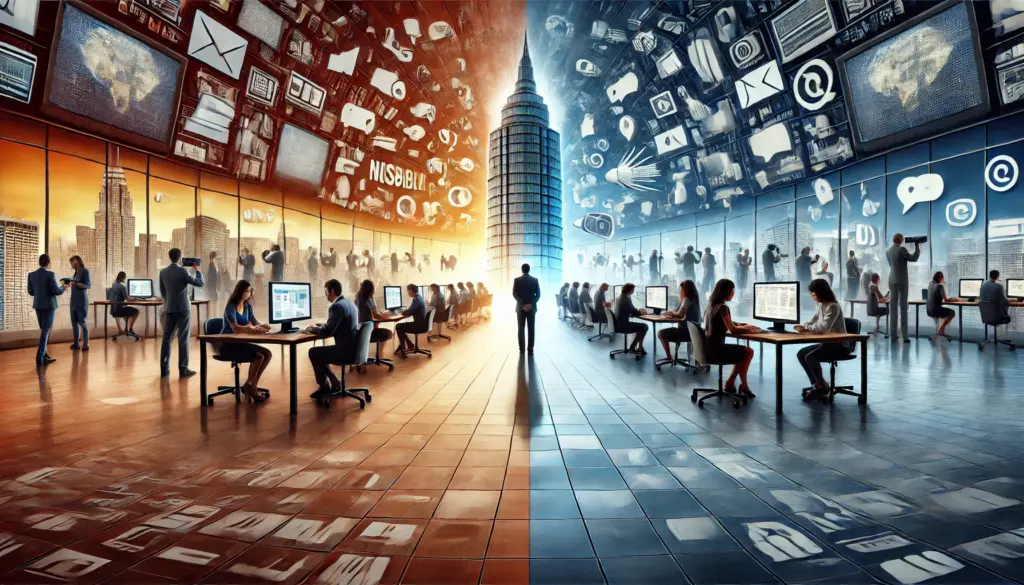
ニューメディアは、誰でも自由に発信できる場として、オールドメディアとは異なる魅力を持っています。
これまでのメディアは、大手企業や政府機関が情報をコントロールしていましたが、今では個人がダイレクトに情報を発信できる時代です。
しかし、自由な発信が可能だからといって、すべての情報が信頼できるわけではありません。
ここで重要なのが、ニューメディアの中にも「フリーメディア」と「カオスメディア」という大きく異なる性質を持つメディアが存在するということです。

フリーメディアとは、企業や政府から独立しながらも、信頼性の高い情報を提供するメディアのことです。
例えば、医師が運営するYouTubeチャンネルでは、健康に関する正確な情報を提供し、専門家としての見解を示しています。また、独立系ジャーナリストが政府や企業の影響を受けずに調査報道を行うケースもあります。

カオスメディアとは、話題性や拡散力を重視し、センセーショナルな情報が優先されるメディアのことです。
たとえば、特定の有名人のスキャンダルを過激なタイトルで煽るYouTube動画や、まったく根拠のない陰謀論を拡散するSNSアカウントが典型的なカオスメディアです。
こうしたコンテンツは、感情を刺激し、人々が拡散しやすい特徴を持っています。

カオスメディアが拡散されやすい理由はいくつかあります。
YouTubeやX(旧Twitter)では、「エンゲージメントの高いコンテンツ」が優先的に表示されます。センセーショナルな情報ほどコメントやシェアが増えるため、より多くの人に届きやすくなります。
人は「驚き」や「怒り」を感じる情報に反応しやすい傾向があります。冷静な分析記事よりも、感情を揺さぶる情報の方が拡散されやすいんです。
YouTubeやXは、視聴時間やエンゲージメントを伸ばすことが収益につながるため、センセーショナルなコンテンツが推奨されやすい仕組みになっています。

ニューメディアには「フリーメディア」と「カオスメディア」の両方が存在します。その中で、私たちがどの情報を信じ、どう行動するかが重要です。
次回は、「炎上した人が消えない時代─テレビとネットの矛盾する倫理観」について考えていきます。お楽しみに!
「炎上した人が消えない時代─テレビとネットの矛盾する倫理観」についてはこちらの記事に書きました。


こんにちは!関達也です。
前回の記事では、「オールドメディア vs. ニューメディア」の対立について考えました。
メディアの分裂、「オールドメディア vs. ニューメディア」の時代についてはこちらの記事に書きました。

かつては、テレビや新聞といったオールドメディアが情報の中心であり、社会全体の共通認識を作っていました。
しかし、YouTubeやX(旧Twitter)、TikTokといったニューメディアが台頭したことで、誰でも発信できる時代になり、「何を信じるか?」が人によって大きく変わってきました。
オールドメディアは、編集や取材を経た情報を発信することで、信頼性の高い情報を提供することを重視してきました。一方で、ニューメディアでは、拡散力が重視され、「バズる」ことが情報の価値を決める要因になりつつあります。
その結果、メディアの分裂が進み、社会の見方や価値観にも大きな違いが生まれています。
この分裂の根本には、「どの情報が正しいか?」という単純な問題だけではなく、「どの価値観を信じるか?」という、より深い対立があります。
今回は、岡田斗司夫さんが提唱した「ホワイト社会」の概念を踏まえながら、「ルール社会 vs. ストーリー社会」という新たな価値観の分裂について考えていきます。

かつて、テレビや新聞(オールドメディア)が社会の共通認識を作っていました。
しかし、ニューメディアの台頭で「何を信じるか?」が人によって違う時代になりました。
この変化の背景にあるのが、「ルール社会」と「ストーリー社会」の価値観の違いです。
岡田斗司夫さんが提唱した「ホワイト社会」は、まさにルール社会の一部でした。
ホワイト社会についてはこちらの記事に書きました。

しかし、現代では「ホワイト社会」の枠を超えたストーリー社会が力を持ち始めています。

ルール社会とは、一言で言えば「事実・論理・規則を最優先する社会」です。
オールドメディアはこのルール社会の価値観を基盤にしていて、たとえばニュース報道では「事実確認をしてから伝える」「中立性を意識する」といった基準を持っていますよね。
でも、このルール社会に対抗するように、今の時代に台頭してきたのが「ストーリー社会」なんです。

ストーリー社会は、「正しさよりも納得感が大事」な社会です。
ニューメディアは、このストーリー社会の性質を強く持っています。たとえば、YouTubeの暴露系動画や、Xで拡散される陰謀論などは「事実」よりも「物語として面白いかどうか」が重要視される傾向にあります。
だからこそ、ルール社会とストーリー社会は衝突しているんです。

今、社会の中で「事実を重視するルール社会」と「共感を重視するストーリー社会」の対立がどんどん深まっています。その理由はいくつかあります。
かつては、ほとんどの人がテレビや新聞を通じて情報を得ていました。でも、今はYouTubeやSNSが普及し、誰でも情報発信ができる時代になっています。
結果として、「ルールに基づいた事実を伝えるメディア」と「ストーリーを重視するメディア」が分裂し、人々もそれぞれ自分の価値観に合ったメディアを選ぶようになりました。
ストーリー社会では、「注目されること」が最も大きな武器になります。そのため、事実よりも「バズるかどうか」が優先される傾向がありますよね。
一方で、ルール社会では「信頼性が最優先」なので、拡散力ではストーリー社会に勝てません。このギャップが、両者の対立を加速させています。
YouTubeやXのアルゴリズムは「人々が興味を持ちそうな情報」を優先的に表示します。その結果、「感情を刺激するストーリー」が拡散されやすくなり、ますますストーリー社会が勢力を伸ばしているんです。
では、ルール社会とストーリー社会、どちらが正しいのでしょうか?
実は、この二つはどちらも必要なんです。
さて、次回は「ニューメディアの中の分類 ─『フリーメディア』と『カオスメディア』」について考えていきます。お楽しみに!
「ニューメディアの中の分類 ─『フリーメディア』と『カオスメディア』」についてはこちらの記事に書きました。
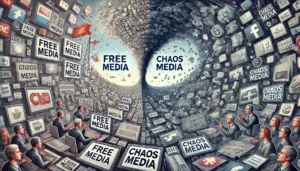

こんにちは!関達也です。
最近、テレビを見なくなったという人、増えてますよね。
僕の周りでも、ニュースはYouTubeやX(旧Twitter)でチェックする、エンタメはNetflixやTikTokという人が多くなっています。
昔は、みんなが同じ時間にテレビを見て、同じ新聞を読んでいた。でも今は、それぞれが好きなメディアを選び、異なる情報空間に生きています。
つまり、メディアが分裂し、それに伴って社会の見え方も変わってきているんです。
オールドメディアというのは、テレビや新聞、雑誌など、昔からあるマスメディアのことです。特徴としては、
一方、ニューメディアはYouTubeやX、TikTok、個人ブログなど、ネットを活用したメディアのことです。こちらは、
こうして並べると、オールドメディアの「信頼性」とニューメディアの「拡散力」という対比がよく分かりますよね。

昔は、テレビと新聞だけを見ていれば、大体の人が同じ情報を共有していました。でも、今は違います。
例えば、同じニュースでも、
このように、オールドメディアは「事実を伝える」ことを重視するのに対し、ニューメディアでは「意見」や「感情」が重視される傾向があります。
その結果、人々は自分の価値観に合ったメディアを選ぶようになり、社会全体が「分断」されていくんです。

オールドメディアの良さは、取材や編集を経ているため、情報の正確性が比較的高いことです。でも、スピード感がないし、スポンサーや政治の影響を受けることもあります。
一方、ニューメディアは圧倒的な拡散力がありますが、フェイクニュースや偏った情報が広がりやすいリスクもある。例えば、YouTubeの暴露系チャンネルや、Xでバズる陰謀論などですね。
じゃあ、どちらが正しいのか?
実は、これからの時代に求められるのは「どちらも活用できる力」なんです。
オールドメディアの信頼性を参考にしつつ、ニューメディアのスピード感や双方向性を生かす。つまり、「情報リテラシーを高めて、メディアを使いこなすこと」が大事なんです。

メディアが分裂し、誰もが好きな情報だけを信じる時代になりました。でも、これが進むと「分断」が深まり、社会全体の共通認識がなくなっていく。
だからこそ、僕たちに必要なのは「情報の取捨選択をする力」なんです。
これからの時代、「情報を鵜呑みにせず、考えられる人」が強くなります。
さて、次回は「ホワイト社会」の影響力がますます強くなる中、今の社会では「ルール社会 vs ストーリー社会」の対立が深まっています。
次回は、この分裂がどこから生まれ、どこに向かうのかを考えていきます。お楽しみに!
ホワイト社会が強まる時代に「ルール社会 vs ストーリー社会」の分断が生まれていることについてはこちらの記事に書きました。


こんにちは!関達也です。
僕は最近まで、韓国のユン・ソンニョル大統領のことを、正直「かなり危ないリーダー」だと思っていました。
日本のメディアを通して見る限り、「戒厳令を出した」「独裁者化している」「逮捕された」など、悪い印象しか入ってこなかったんです。
でも、あるYouTube動画を見て、その見方が大きく揺らぎました。
そこには、韓国の若者たちがユン大統領を支持し、「民主主義を守れ」と叫びながらデモをしている姿が映っていたんです。
▼この動画です。
この動画を見て、「え?ユン大統領を応援してるの?あんな悪者じゃなかったの?」と衝撃でした。
この経験から僕は、「これはメディアの報道の仕方に何か問題があるのではないか?」と感じて、韓国のメディア事情を調べてみることにしました。

調べていくと、韓国のメディアはかなり極端に「左派」と「右派」に分かれていることがわかりました。
左派メディア(進歩系)にはハンギョレ新聞やKBS、MBC、JTBCなどがあり、これらはユン大統領に非常に批判的です。
逆に、朝鮮日報や東亜日報、TV朝鮮といった保守系メディアはユン大統領を擁護する姿勢が強いんです。
つまり、同じニュースでも、どのメディアを読むかによって「全然違う話」に見えるということです。
あるメディアでは「独裁者ユン」、別のメディアでは「国を守る英雄ユン」。
これって、ちょっと異常な状況ですよね。

一方で、日本のメディアも偏向がないとは言えません。ただし、韓国ほど極端ではない印象です。
たとえば、朝日新聞や毎日新聞はリベラル寄りで、読売新聞や産経新聞は保守寄りという傾向はあります。
でも、韓国のように「政権が変わったらメディアの報道姿勢も180度変わる」とまではいかないんです。
とはいえ、日本のメディアにも課題はあります。特に、韓国や中国など近隣国の報道において、「深掘りが足りない」「一方的な視点に偏りがち」だと感じることが多いんです。
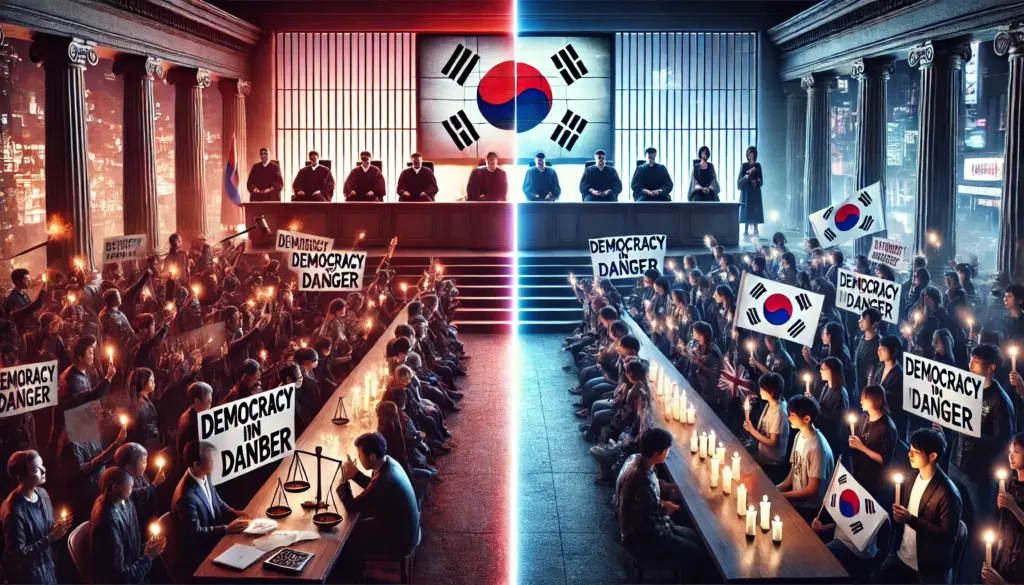
今回の騒動の中心にある「戒厳令」についても、左派メディアは「民主主義の危機」と大々的に報じました。実際にユン大統領はその後、内乱罪で逮捕されています。
これだけを見ると「やっぱり悪いやつだったんだ」と思うかもしれません。
でも一方で、右派メディアやSNSでは「左派が裁判所とメディアを支配してユン大統領を排除した」という主張も出てきています。
若者たちがデモをしてまで彼を支持しているという事実も、無視できない現実なんです。
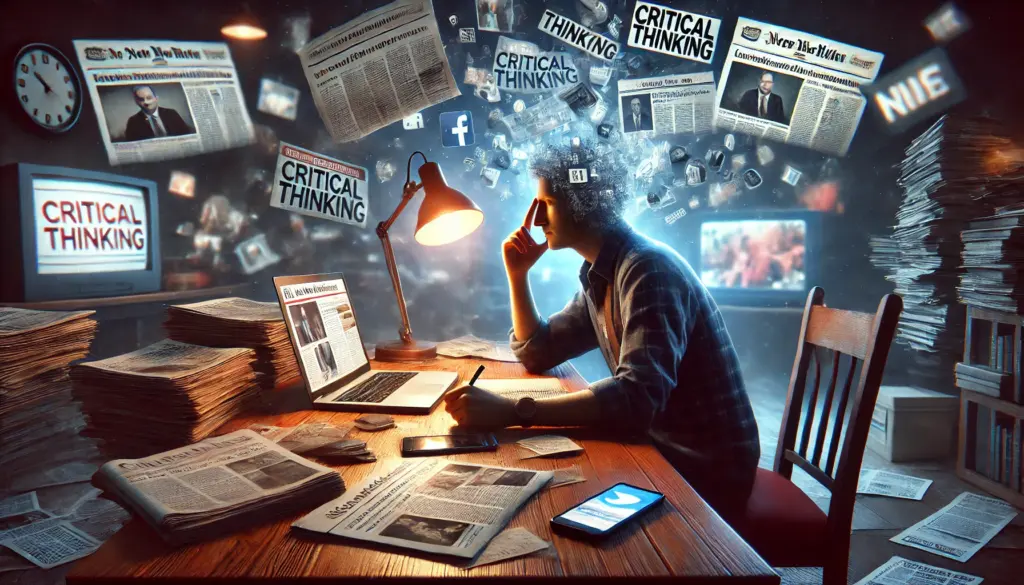
韓国の状況を見ていて、僕は「情報ってほんとに怖いな」と思いました。
どこから情報を得るかで、世界の見え方が全く変わってしまうからです。
最近では、韓国の若者の中にも、YouTubeやSNSを通じて「左派メディアの偏向」に気づき、別の視点を持つ人たちが増えているそうです。これは、日本でも同じですよね。
テレビや新聞だけでなく、自分で情報源を選び、比較しながら考える姿勢がますます大事になっています。
韓国のメディア事情を見て、「報道されていること=真実」ではないと、改めて感じました。これは日本に住む僕らにとっても他人事じゃありません。
僕は、たまたま今回のYouTube動画をきっかけに韓国の状況に疑問を持ちましたが、多くの人は「テレビで言ってたから」「新聞に載ってたから」で判断してしまいがちです。だからこそ、今の時代は「自分の頭で考える」ことが本当に大事なんだと思います。
あなたは、ユン大統領の報道をどう見ましたか?
僕はこれからも、メディアの報道を鵜呑みにせず、いろんな視点を自分で調べて、自分なりの答えを出していきたいと思っています。

こんにちは!関達也です。
前回、AI時代に埋もれないためには、「熱量」が大事ということをこちらの記事に書きました。

でも、「そもそも熱量がない」状態の人はどうすればいいのでしょうか?
やりたいことが見つからない。何を頑張ればいいか分からない。何に熱くなれるのかピンとこない。そんなふうに感じている人は意外と多いと思います。
でも安心してください。
熱量って、持って生まれた才能じゃないんです。「熱量は作るもの」なんですよ。
今回は、その熱量をどうやって生み出すのか? どうやったら「自分の中の炎」を燃やせるのか?具体的な方法を解説していきます。
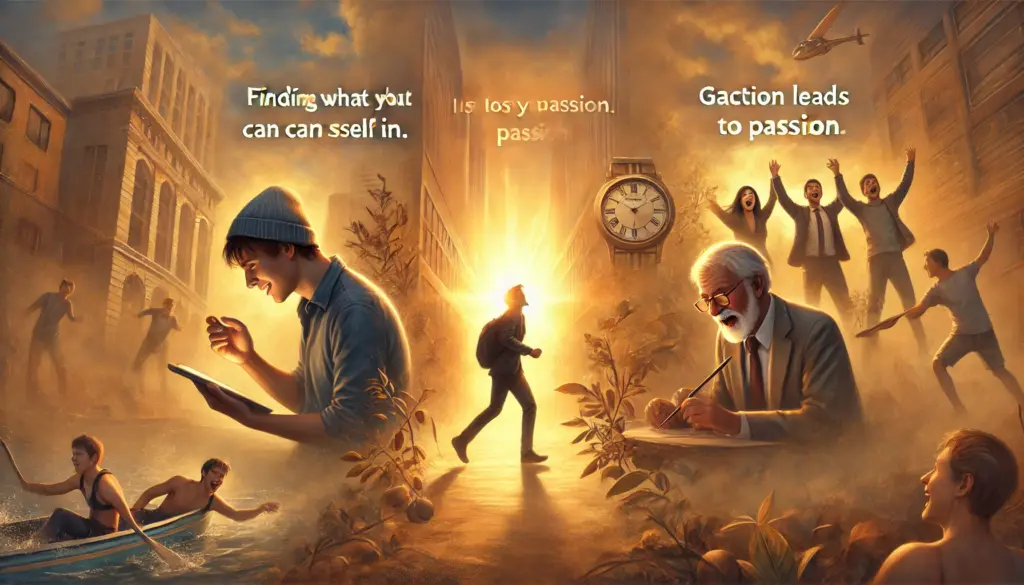
まず大前提として、「いきなり熱くなれるものを探そう」としないことです。熱量って、湧き出るものじゃなくて「積み重ね」で生まれるんです。
「やりたいことが分からない」という人は多いけど、気づいたら時間を忘れてしまうことってありませんか?
こういう「没頭できるもの」の中に、熱量を生み出すヒントがあるんです。
「好きだから続ける」んじゃなくて、「続けてるうちに好きになる」こともある。まずは、自分が自然と時間を使ってしまうものに目を向けてみてください。
「熱量があるから行動できる」と思っている人が多いけど、実は逆なんです。
「行動するから、熱量が生まれる」
たとえば、筋トレ。最初は面倒だし、つらいだけ。でも続けてると、体が変わってくる。それが楽しくなって、「もっとやりたい!」って思えてくる。
ブログやSNS発信だって同じ。最初は誰にも読まれなくて虚しいけど、少しずつ反応が増えてくると「面白い!」って思えてくる。
だから、「熱くなれるものがない…」と思っても、とにかく小さく行動することが大事です。
1人でやっていると、なかなか熱量は生まれにくいんです。
でも、仲間がいると話は別。たとえば…
人と関わることで、熱量はどんどん高まっていくんですよね。
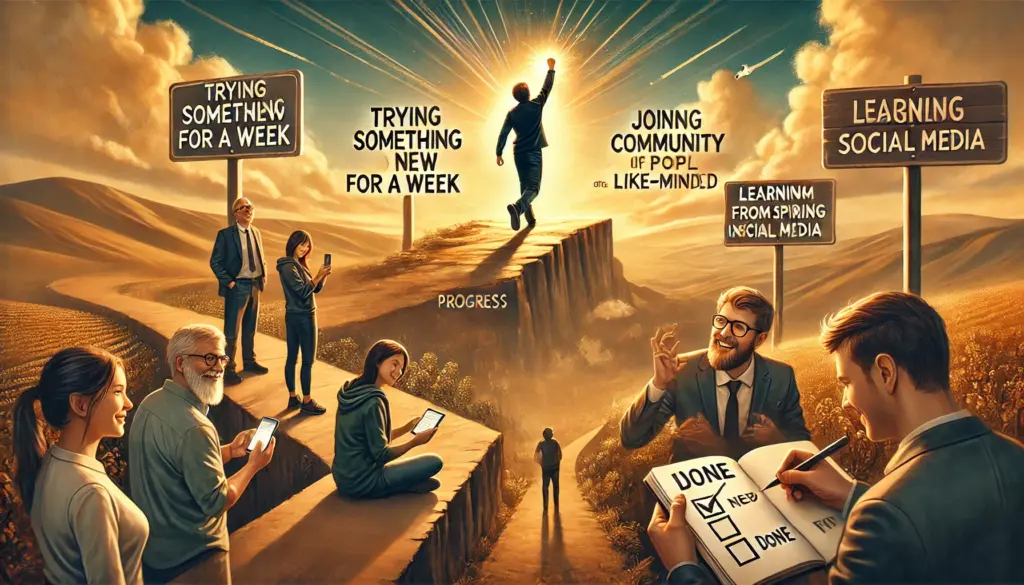
「じゃあ、どうやって動けばいいの?」という人のために、すぐにできる5つのアクションを紹介します。
「やりたいことが見つからない…」と言っているだけでは何も始まりません。とりあえず1週間、何かやってみる。
すると、続けるうちに「面白い!」と思える瞬間が必ず出てくるんです。
1人で悩むより、同じ興味を持つ人とつながったほうが早い。
X(旧Twitter)やFacebookのグループ、オンラインサロンでもOK。「この人たち、面白いな」と思える場所に飛び込んでみると、刺激を受けて自分の熱量も上がります。
人は、小さな成功を積み重ねるとどんどん楽しくなってくる。
「まずは小さく成功すること」が、熱量を生み出すカギです。
人に見られることで、「もっと頑張ろう!」という気持ちが生まれます。
最初は小さなことでも、発信することで「やらなきゃ!」という責任感が生まれて、それが熱量に変わるんです。
「この人すごい!」と思う人の行動を真似してみるのもアリ。
最初は真似でもOK。やってるうちに「自分らしさ」が生まれ、熱量がどんどん湧いてきます。

「自分には熱量がない…」と思っている人も、動き出せば変わります。
大事なのは、「いきなり熱くなれるものを探さないこと」「とにかく動いてみること」。
まずは1つ、気になることを試してみませんか?

こんにちは!関達也です。熱量はどうやって生まれる?
AIが次々とコンテンツを生み出す時代になりました。文章、音楽、動画、イラスト、果ては音声まで、AIはどんどん人間が作るものに近づいています。
これから先、AIの技術はさらに進化し、ますます高品質なコンテンツが量産されるでしょう。
じゃあ、人間にしかできないことって何なのか? どうやったらAIに埋もれず、自分のコンテンツや発信を差別化できるのか?
それが「熱量」なんです。
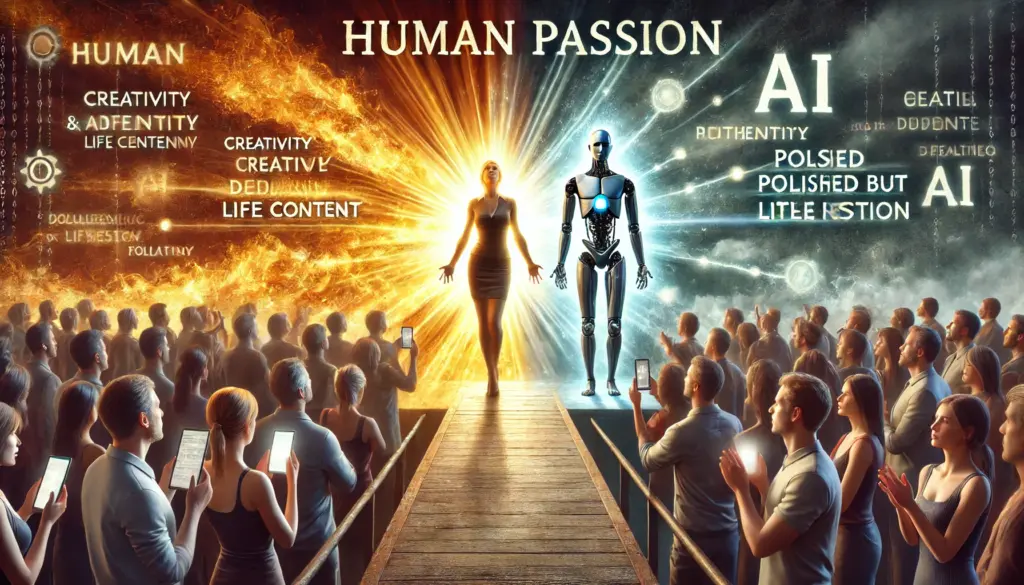
AIは過去のデータをもとに最適解を導き出し、それっぽいコンテンツを作ることは得意です。
でも、そこに「想い」や「情熱」はないんですよね。
たとえば、誰かの心に深く刺さる言葉って、単にうまくまとまっているからではなく、「その人が本気でそう思っているかどうか」で決まります。「この人の言葉だから響く」「この人がやっているから応援したい」と思われるのは、その人の熱量が伝わるからです。
熱量がある人のコンテンツは、見る人、聞く人の心を動かします。逆に、どんなにキレイにまとめられた文章でも、感情がこもっていなければ「なんか薄っぺらいな」と感じられてしまうんです。
だからこそ、これからの時代に求められるのは、情報の正確性や完成度ではなく、「どれだけ本気で伝えようとしているか?」という部分なんです。

「熱量が大事」と言われても、どうやってそれを伝えればいいのか分からない人も多いですよね。
どこで、具体的にどうすればいいのかを5つのポイントにまとめました。
人は「共感」したときに心を動かされるものです。「なぜこのテーマにこだわるのか?」「自分がどんな経験をして、今この考えに至ったのか?」を語ることで、熱量が伝わります。
たとえば、「僕は昔、〇〇に挑戦したけど全然ダメだった。でも□□を経験して、そこから大きく変わったんです」というように、自分のリアルな体験を入れるといいですよね。
「嬉しい」「悔しい」「楽しい」「辛い」といった感情をちゃんと表現することも大事です。
AIが作る文章って、どうしても淡々としているんですよね。だからこそ、人間らしい感情を文章や声に乗せることで差別化できます。
「本当に悔しかった」「マジで嬉しかった」みたいな、自分が感じたことを素直に書くと、熱量が伝わりやすいんです。
熱量がある人って、考えているだけじゃなく、実際に行動しているんですよね。
たとえば、「僕はこのテーマについてずっと考えていたけど、悩むくらいならやってみようと思って〇〇を始めた」とか、「いろいろ試した結果、□□が一番効果的だった」といった話は、すごく説得力が出ます。
行動を伴わない言葉は、どれだけ立派でも薄っぺらく聞こえてしまうんです。
AIが作る文章は、文法的に正しく、きれいに整っています。でも、逆に言えば「ちょっと堅苦しい」「無難すぎる」ものになりがちなんですよね。
だからこそ、人間ならではのリアルな言葉を使うことが大切です。
「これ、マジですごいんですよ!」「いや、ホントにヤバいって思った」みたいな、会話のような表現を入れると、一気に熱量が伝わりやすくなります。
文章だけじゃなく、動画や音声を使うと、より直接的に熱量を伝えられます。
特にYouTubeやポッドキャストなら、声の抑揚や話し方ひとつで、どれだけ本気で語っているのかが伝わるんですよね。
「文章では伝えきれない部分」をカバーするために、発信方法を工夫するのも大事です。

AIの進化によって、誰でも簡単に高品質なコンテンツを作れる時代になりました。でも、その中で埋もれずに生き残るためには、「熱量」が絶対に必要です。
情報をまとめるだけでは、AIには勝てない。でも、「なぜ自分がこれを伝えたいのか?」を本気で語れる人は、唯一無二の存在になれます。
あなたはどうやって自分の熱量を伝えますか?
次に、熱量がない人でも、今すぐ熱量を生み出す方法をこちらの記事に書きました。
